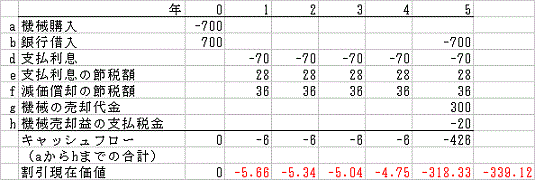
最近になってリース会計基準は国際会計基準(IFRS16)や米国会計基準(ASC842)が新たに公表されて大きく変わってきており原則としてオペレーティングリースであれキャピタルリースであれ借り手は資金調達して資産を購入したと同様の会計処理が必要となった。日本でも企業会計基準委員会からリースに関する会計基準(案)が2023年5月2日に公表されている。(https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.html を参照)。日本でも1~2年の準備期間の後に会計基準が適用されるだろう。今後税法もどのような改正がされるか予想できないが、とりあえず現行の制度が続くと仮定して考えてみる。
借り手の立場から見て、自ら設備を購入するか、またはリースの利用する方が有利かという判断をする場合がある。ここで借り手にとって、リースは一連のキャッシュの支払フローと見れば借入と代替的な関係にあると考えられる。
このような場合には、自ら設備を購入するプロジェクトとリースによるプロジェクトのキャッシュフローの現在価値を比べ、より支出額の現在価値が少ないほうが借り手にとって有利な選択となる。リースと借入は代替的とすれば両者のキャッシュフローのリスクも同程度であり適用する割引率も負債の利子率と同じと考えられる。
次に、キャッシュフローで見る場合には税金がかかる場合には費用の節税効果を考慮しなければならない。節税効果とは税金の計算上で費用が損金(税法上の費用損失等を意味する)と認められれば、税金が(費用×税率)分だけ安くなり税金支払というキャッシュ支払がその分だけ低くなることを言う。節税効果というと何か税法の裏技を使って税金支払を低く抑える好ましからぬことと考える人もいるかもしれないが、ここで言う節税効果とはそのようなことではなくtax shieldつまり、損金となれば損金×税率分だけ税金支出のキャッシュ・アウトフローが少なくなることを意味する。我々の世界では支払利息は損金となるので、支払利息も節税効果があり、節税効果を織り込んだ税引き後の利子率は利子率×(1-税率)に等しくなる。現在価値計算をする場合には分子のキャッシュフローを税引き後で把握すれば適用する割引率も税引き後の利子率となる。分子のキャッシュフローが税引き前であれば適用する割引率も税引き前の利子率となる。減価償却費は現金支出が伴わない費用であるが節税効果があり減価償却費×税率 の分だけ税金支払を低くする。このような点を踏まえて簡単な設例で購入かリースかの経済計算を検討してみる。
設例による経済性の検討
B株式会社は製造ラインに新しい機械を導入する計画を立てている。機械の購入価額は700百万円、耐用年数7年(残存価額70百万円)である。その製造ラインは5年後には廃止し、その時点で機械を売却処分する予定である。現時点での5年後の見積売却価額は300百万円である。B社は機械の購入代金を銀行借入で700百万円を調達する計画で、借入条件は借入期間5年、金利は税引き前で10%、元金は5年後に一括返済、金利は毎年度末に支払うことになっている。(元利均等返済の条件にすると計算が複雑になるので、元金一括返済としてある。)B社は減価償却を定額法で行っており、B社の税率は40%である。
このような計画を立てている時にリース会社より同一の機械を5年間リースするという提案があった。リースの条件は5年間のリースで毎年のリース料(年払い)は130百万円でリース開始時にリース料を支払い、以後は毎年度の期首に支払うことになっている。このリース料は税法上も損金として認められるとする。
ここで銀行借入により機械を購入した場合のキャッシュフローを整理すると
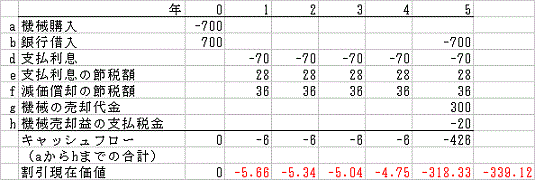
期初の時点でのキャッシュフローは借入(入金を+、支出をーで表示している)入金と購入代金支出とが同時に発生するのでネットのキャッシュフローはゼロとなる。支払利息と減価償却費には節税効果があり、プラスのキャッシュフローとして表示されている。例えば、支払利息は700百万円×税引前利子率10%=70百万円、これに対する節税効果は70百万円×40%=28百万円。減価償却費は定額法によるので(700-70)÷7=90、これに対する節税効果は90×40%=36。
5年後の投資期間の年末には機械を300で売却するが、これにより売却益が50生ずる。これに対しては40%の税金が課せられるので20=50×40%の現金支出が生じる。下表参照
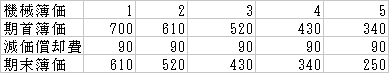
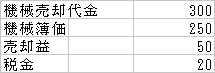
各年のキャッシュフローを税引後割引率6%(10%×(1-40%))で割引いて現在価値を計算すると-339.12となる。
なお、現在価値計算は下記による。
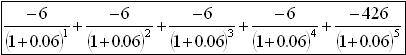
=-339.12
リースを利用した場合のキャッシュフローを整理するとリース料支払は期初0から始まるので下表のようになる。
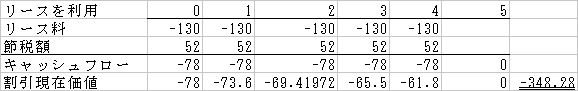
リース料が130の場合はキャッシュアウトフローの現在価値は購入のほうがリースよりも小さくなる。(購入 339.12 < リース 348.28)
従って、ここではリースを利用せずに購入したほうが経済計算上は有利となる。
B社にとってリース料が有利となる分岐点を求めるには、
リース料をxとすれば税引後のリース料は (1-0.4)x となるので
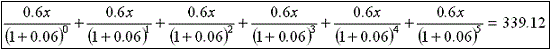
このようなリース料であれば購入した場合の現在価値と等しくなる。
ここで、上式を解くと x=126.58 を得る。従ってリース料が126.58以下であれば購入よりもリースが有利となるが130では126.58を超えているのでリースは不利と判断できる。
ところで、上記の例では機械の5年後の売却価格を300と予想していたが、陳腐化の速度が予想よりも早く5年後の時価が100とした場合には自社購入の現在価値はどうなるであろうか。5年後の最終年のキャッシュフローが変わるだけだが。表にすると
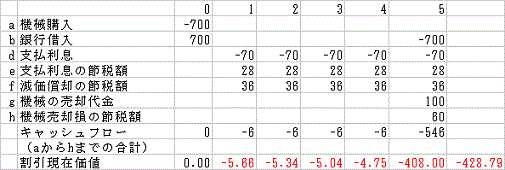
5年後の機械売却によるキャッシュフローは
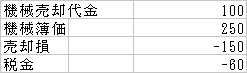
時価が100に下がったために売却損が150生じるが、これは課税所得を減らすので40%の節税効果60(150×40%)が生まれる。
機械の予想売却価額が100の時には上記の表のように自社購入の現在価値は-428.79となる。これはリースの場合の現在価値-348.28を大幅に上回るため、明らかにリースを利用した方が有利となる。
リース期間満了時の機械の売却時価を残価というが、自社購入の場合はこの残価の変動リスクを自ら負うことになる。この残価リスクを回避したければリースを利用すればよい。この場合は残価リスクは貸し手であるリース会社に転嫁される。もちろん、リース会社も残価リスクを負担するには相当のリスクプレミアムをリース料に上乗せするのでリース料はその分だけ高くなる。ここでいえることは借り手であるB社が十分な情報を持っていて残価の不確実性リスクを貸し手のリース会社よりも低く抑える実力があれば自社購入が有利であるが、一般的には機械等の物件や売却市場の情報では貸し手であるリース会社のほうが優れていると考えられる。ここで借り手から見ればリース料がアップした分は投資期間後に中古市場で機械を一定価額で売却するプット・オプションの購入代金と見ることもできる。リアルオ・プションで言えば中止オプションの権利を得て残価リスクをヘッジしたと同様の経済効果を得たと考えることができる。この意味で借り手にとってはリースは残価リスクを回避したり低減さすメリットがあるといえる。
借り手にとってはリースと購入の何れが有利か判断する場合には、購入の場合とリースの場合の現在価値を比較して決定することになるが、購入して所有すれば、資産の維持管理にコストがかかり、しかも処分時に残価リスクを自ら負うことになるので、これらをどう評価するかも重要なポイントとなる。
借り手にとっての経済計算では伝統的な割引キャッシュフロー法(DCF)が用いられるが、現代のように変化が激しい時代にはDCF法だけでは経営判断を誤る危険がある。
ある事業を始めたが収益性が予想よりも低い時には早期に撤退したり事業転換する必要がある。予想より収益性が高ければ直ちに事業を拡大することも必要となる。技術進歩が早く陳腐化が激しく、消費者の嗜好が変りやすいといった、さまざまな変化の激しい時代には経営の柔軟性(flexibility)を確保していないと、企業は存亡の危機に直面しかねない。その意味で、リースは中途解約の損害金を負担したとしても企業経営に大きな柔軟性を提供している。多額の設備投資をし、いざ撤退や業種転換するときにそれを売却する手間や出費を考えると柔軟性を確保するメリットは大きい。借り手としては伝統的なDCF法で経済計算するとともに事業プロジェクトの特性からどの程度の柔軟性が必要かを判断したうえでリースか購入かを決定する必要がある。
なお、会計基準等の改正・変更がリースのメリット・ディメリットに及ぼす影響については下記で簡単な検討を行っている。